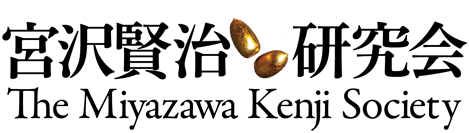| 例会時間割 | ||
| 開催日 | 令和7(2025)年4月5日(土) | |
| ※ 今回は会場(氷川区民会館)を確保しています。また、リモート形式の配信も行います。リモート例会お問合せフォームより申込みいただいた方に招待状を送付します(下記の説明を参照願います)。 | ||
| 開始時間 | 所要時間目安 | 内 容 |
| 13:00~ | 30分 | 開場 氷川区民会館 、Zoomアカウント開始、案内等 |
| 13:30~ | 1時間程度 | 研究発表 大塚常樹氏(会場対面予定) |
| 14:30~ | 20分程度 | 質疑応答(〃) |
| 14:50~ | 15分程度 | 休憩・案内 |
| 15:05~ | 1時間程度 | インタビュー 名取佐和子氏「銀河の図書室」 インタビュワー 大島丈志(会場対面予定) |
| 16:05~ | 20分程度 | 質疑応答(〃) |
| 16:30 | 終了、退出 | |
| 17:00~ | 対面とリモートの混合方式の場合はリモートの懇親会はありません。 | |
| ※特に参加費は必要ありませんが会員限定です。会員でない場合はどうしたらよいか? | ||
| ※ |
※ 前後半共々会場対面の予定です。リモート配信はあります。会場は氷川区民会館です。
前半 演題と発表者 演題 宮澤賢治の言語戦略―フィナーレ 大塚常樹(おおつか・つねき)氏
私は2010年から、賢治が自身の思想を読者に効果的に伝えるために、言葉がもつ様々な要素や効果をどのように駆使したのかを「言語戦略」という名で研究テーマとし、その見取り図を本研究会で発表してきた。これまでに、賢治が法華信仰、妙見信仰と法華経の象徴としての白い蓮を別の白い花に置き換えるなど表面に出ないようにしてきたこと、語りの方法として枠物語や、逸脱する語り手、信頼出来ない語り手などをうまく使い分けたこと、オノマトペでD音等の濁音の、大きいものから出る低音という音象徴を効果的に使っていること、「~のもの」という種と類の関係を利用した提喩を使って同じ性質をもつ個別例同士の関係へ想像力を喚起させていること、幻想的な話や虚構とリアルな現実との境界を巧みに設定して、読者にリアリティを感じさせる工夫をしていること、これらを論文化した。言語戦略として最後に残されているのは、賢治が物語の最後にどのような決着を付けているかである。賢治テクストは、既成の価値観を異化、あるいは反転させることで世界のあり方を根本から変える戦略を基底に持っている。それには物語の最後にどのような反転、どのようなメッセージを読者に伝えるのかが重要である。論者は詩人として活動をしているが、詩の良し悪しは最後のフレーズで決まると考えている。言語戦略は対読者戦略でもあり、本テーマ追究のフィナーレとして、賢治テクストの「終え方」の戦略を考えてみたい。
(詩人〈日本現代詩人会会員〉、お茶の水女子大学名誉教授)
※会場における対面による発表+リモート配信。
(詩人〈日本現代詩人会会員〉、お茶の水女子大学名誉教授)
※会場における対面による発表+リモート配信。
後半 演題と発表者 演題 『銀河の図書室』の作者・名取佐和子(なとり・さわこ)さんにインタビュー
4月例会の後半では、宮沢賢治の作品をモチーフに現代の高校生活を描いた『銀河の図書室』の作者・名取佐和子さんにインタビューを行います。
名取佐和子さんは、ゲームシナリオライターを経て小説家に転身。兵庫県神戸市に生まれ、神奈川県藤沢市に育ち、2015年に『ペンギン鉄道なくしもの係』でエキナカ書店大賞受賞。2024年8月刊行の『銀河の図書室』では、「宮沢賢治」を研究する高校生の「イーハトー部」の活動を描き、話題を集めています。
名取さんの作品には、『金曜日の本屋さん』(2018年2月)で「銀河鉄道の夜」が取り上げられ、『銀河の図書室』では「銀河鉄道の夜」と「ほんとうの幸」が物語の鍵となっています。また、読書や図書室の重要性も作品を通じて繰り返し描かれます。今回のインタビューでは、名取さんが宮沢賢治作品とどのように出会ったのか、『銀河の図書室』の創作と宮沢賢治作品とのかかわり、『銀河の図書室』へ込めた想い、そして図書室の役割やこれからの読書に関してお話を伺いたいと思います。
インタビュー 大島丈志 文教大学教授
※ 会場における対面による発表+リモート配信。
名取佐和子さんは、ゲームシナリオライターを経て小説家に転身。兵庫県神戸市に生まれ、神奈川県藤沢市に育ち、2015年に『ペンギン鉄道なくしもの係』でエキナカ書店大賞受賞。2024年8月刊行の『銀河の図書室』では、「宮沢賢治」を研究する高校生の「イーハトー部」の活動を描き、話題を集めています。
名取さんの作品には、『金曜日の本屋さん』(2018年2月)で「銀河鉄道の夜」が取り上げられ、『銀河の図書室』では「銀河鉄道の夜」と「ほんとうの幸」が物語の鍵となっています。また、読書や図書室の重要性も作品を通じて繰り返し描かれます。今回のインタビューでは、名取さんが宮沢賢治作品とどのように出会ったのか、『銀河の図書室』の創作と宮沢賢治作品とのかかわり、『銀河の図書室』へ込めた想い、そして図書室の役割やこれからの読書に関してお話を伺いたいと思います。
インタビュー 大島丈志 文教大学教授
※ 会場における対面による発表+リモート配信。
※ 今回のインタビューにおいては必然的に「課題図書」的な扱いとなりますので、可能な限り事前の読了をお願いします。入手先の一例を示しておきます。
※ リリース案内文
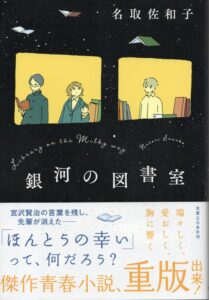
■リモート例会のお申し込みについて/コロナ下における例会開催についての説明