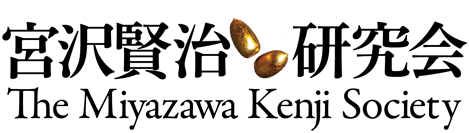| 例会時間割 | ||
| 開催日 | 令和5(2023)年4月1日(土) | |
| ※ 今回は、お二人ともリモート形式のご発表です。会場の用意はありません。会場はキャンセルしました(3月19日変更)。web例会お問合せフォームより申込みいただいた方に招待状を送付します(下記の説明を参照願います)。 | ||
| 開始時間 | 所要時間目安 | 内 容 |
| 13:00 | 30分 | 開場、Zoom接続開始、案内等 |
| 13:30 | 1時間程度 | 例会発表・前半 小島聡子氏、リモート発表。 |
| 14:30 | 15分程度 | 質疑応答(〃) |
| 14:45 | 15分程度 | 休憩・案内 |
| 15:00 | 1時間程度 | 例会発表・後半 大嶋 仁氏、リモート発表。 |
| 16:00 | 15分程度 | 質疑応答(〃) |
| 渋谷会場の利用がなくなりましたので、リモート懇親会が可能となりました。時間の許す方は参加をお願いします。(3月19日変更) | ||
| ※特に参加費は必要ありませんが会員限定です。会員でない場合はどうしたらよいか? |
※ 午後時間の開催です。
※ 今回は、発表者お二人がリモート形式によるため、会場は用意しないこととしました(3月19日変更)。氷川区民会館はキャンセルしました。
前半 演題と発表者 宮沢賢治の使う「標準語」―気づかない方言について― 小島聡子(こじま・さとこ)氏
明治時代後半から昭和初期は、日本の言語政策として「標準語」が企図され浸透させられてきた時代である。宮沢賢治はその時代に生きた人であり、「標準語」と対峙させる形で方言を意識していたことは書簡などからも窺われ、作品に意図的に方言を用いたものがあることもよく知られている。ただそれでも多くの作品は基本的には「標準語」で書かれている。しかし、その「標準語」で書かれたはずの作品の中に、現代の私たちが読むと違和感のある表現は少なくない。そのような表現は、時に宮沢賢治の独特な表現と評価されたり、あるいは単に少し古い言葉遣いと看過されたりすることもあるようだが、本発表では、そこに少なからず方言の影響がみられることを紹介する。また、そのような「気づかない方言」に、ほとんどが「標準語話者」と自認する現代の学生たちは気づくのかどうか、岩手大学の授業での反応も紹介し、現在の日本の言語状況、方言のありようについても触れる。
(岩手大学人文社会科学部教授)※リモートによる発表です。
(岩手大学人文社会科学部教授)※リモートによる発表です。
後半 演題と発表者 「賢治の心理学と地質学」 大嶋 仁(おおしま・ひとし)氏
宮沢賢治における心理学は心象の科学的記述に基づくものであり、彼はその記述をもとに心理学を構築するつもりであった。彼は心の動きを物理法則に基づくものと捉えていた一方、心理学をもって科学の究極と考えていたようだ。
賢治が心理学に開眼したのはジェイムズに触れたからだと推測できるが、フロイトにも関心を持っていた形跡がある。しかし、その関心は法華経的世界観ともつながっており、彼にとって心理学を完成することは、法華経を心の科学によって基礎づけることを意味したようだ。
一方、賢治にとっての地質学は、岩石や地層をもとに地球と生物を考える土台となっている。彼は近代的な人間中心主義によってではなく、もっと巨きな視点にもとづいて人類や地球の歴史を考えたのである。アインシュタインの相対性理論がこの視点を補強するのに役立っていることは興味深い。
賢治は近代科学に強い関心を持っていたが、それが世界を幸福にするとは思っていなかった。世界全体が幸福になるには科学が宗教と一致する必要があると見たのであり、であればこそ、法華経を科学によって基礎づけたかったのである。
(福岡大学名誉教授)※リモートによる発表です。
賢治が心理学に開眼したのはジェイムズに触れたからだと推測できるが、フロイトにも関心を持っていた形跡がある。しかし、その関心は法華経的世界観ともつながっており、彼にとって心理学を完成することは、法華経を心の科学によって基礎づけることを意味したようだ。
一方、賢治にとっての地質学は、岩石や地層をもとに地球と生物を考える土台となっている。彼は近代的な人間中心主義によってではなく、もっと巨きな視点にもとづいて人類や地球の歴史を考えたのである。アインシュタインの相対性理論がこの視点を補強するのに役立っていることは興味深い。
賢治は近代科学に強い関心を持っていたが、それが世界を幸福にするとは思っていなかった。世界全体が幸福になるには科学が宗教と一致する必要があると見たのであり、であればこそ、法華経を科学によって基礎づけたかったのである。
(福岡大学名誉教授)※リモートによる発表です。
■web例会のお申し込みについて/コロナ下における例会開催についての説明
ご案内「ホームページの障害発生に伴う対応など」(重要)
2022年1月に、本ホームページに障害が発生した件について説明をしています。(補足説明・修正状況)